但木一真のeスポーツメディア論:eスポーツはスポーツではない!
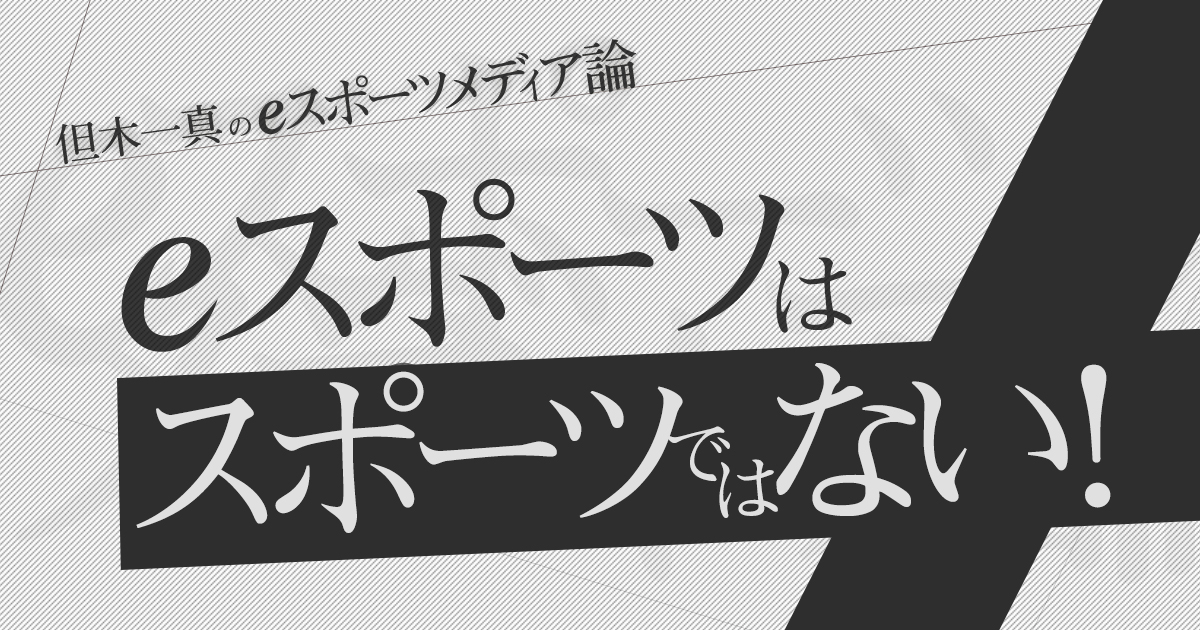
【この記事は約5分で読めます】
eスポーツとゲームのサービス化
2018年7月から行われた「Fortnite Summer Skirmish」は、エピックゲームズによる壮大な実験だった。8週間にわたり毎週開催された大会の第1週、悪夢のようなサーバーラグでまともに動けず、さらに漁夫の利を恐れて積極的に戦おうとしないプレイヤーたち……。Twitchには、大会に対する罵倒の言葉をまき散らすプレイヤーのクリップが大量に投稿された。
エピックゲームズは、大会の直後に「POSTMORTEM(反省)」と題した記事を投稿する。サーバーのパフォーマンス、放送の形式、最終面における偏った建築(トンネルを張り巡らせる戦術)など、改善すべき点について検証し、「フォートナイト」の競技性に疑問を呈する多くのファンに対して釈明を行った。
そこから8週間、エピックゲームズはルールやスコア方式を改訂し、一般プレイヤーの参加といった方式をテストしていった。ビクトリーロイヤルまたはキルによって獲得できるポイントが調整され、終始プレイヤー同士の熱戦が繰り広げられるようになった。
Fortnite Summer Skirmishは、フォートナイトを用いたeスポーツシーンを創る過程だった。プロプレイヤーに参加させ、ファンから(罵倒を含む)フィードバックを獲得することで、最適な解が模索されていった。
フォートナイトに搭載されているバトルロイヤルモードは、基本無料でプレイできる。その代わり、スキンやエモート、バトルパスといった追加コンテンツを有償で提供することで開発・運営に要する資金を回収する。このことからわかるとおり、フォートナイトは長期間運営されることを前提としたサービスのようなものだ。ゲーム業界ではこのような形態のゲームを「Game as a Service(ゲームのサービス化)」という用語で表現する。
長期間運営される中でゲームは変化する。新しい乗り物が追加され、武器の強さは調整され、マップは変化する。フォートナイトで勝利を収めるのテクニックや戦術はアップデートのたびに再定義される。プロシーンを形作る実験が終わることはない。サービス化したゲームの宿命は、常に変化を起こし、プレイヤーを飽きさせないことだ。
フォートナイトはサービス化されたゲームの一例に過ぎない。今日、世界でプレイされるあらゆるゲームがサービスとして長期間運営されることを前提としている。これらのゲームにとってeスポーツというプロシーンは、プレイヤーを飽きさせないためのアップデート要素の1つといってもいい。
eスポーツ同様に競技として分類されるものは多くあれど、これほどまでに商業性と直結した競技は他にないだろう。サッカーや野球、チェスや将棋、モータースポーツや競艇など、大企業が関与して巨額の資金が投じられる競技はあるが、競技そのものは誰でも無償でプレイできるパブリックドメインだ。一方、「PUBG」をプレイするには29ドルを支払わなければならない。
eスポーツはスポーツではない
メディアで散々こすられて手垢のついた「eスポーツはスポーツか?」という議論は、eスポーツの肯定的な受容を引き出すためにスポーツという類推を持ち出し、eスポーツはスポーツのように文化的で高尚な取り組みであり、それに取り組む選手はスポーツのそれのように豊かな才能をもった人々である、という結論を引き出すためのたわいもない話。
だが、この議論を持ち出す人に冷や水を浴びせるとしたら、「eスポーツはスポーツではない」と結論づけたい。なぜならば、eスポーツはスポーツと呼称されるあらゆる競技と余りにも違いすぎるからだ。
eスポーツはゲームという土台の上に成り立っている。eスポーツとはサービス化したゲームという商業主義にまみれた商品の基に成り立つ産業である。どれだけeスポーツの高尚な受容を目指す言論を持ち込もうとしたところで、企業が儲からないと判断すれば1つのタイトルのeスポーツプロシーンは終わりを迎える。
これはeスポーツに取り組むチームや選手、関係者を貶めるような言葉ではない。そして彼らをスポーツに携わる人々のように高尚である、と崇める言葉も筆者は持ち合わせてはいない。
eスポーツは、サービス化したゲームの上に成り立っているからこそ面白い。アップデートのたびにメタが変化がし、その変化が新しいドラマを生む。ゲームに本気で向き合うプレイヤーがいるからこそ、新しいアップデートが急速に解釈されていく。その頂点にプロシーンがそびえ立っている。
eスポーツの競技としての魅力は、商業主義と不可分だ。著者はこの新しい競技の形を他のスポーツとの類推によって単純化したくない。ゲームという文化が生み出した競技の形をまったく新しいものとして理解すべきだ。
eスポーツとは新しい競技の形
本記事には「eスポーツメディア論」と冠した。eスポーツに係る言論を司るメディアがゲームから逃げてほしくないとの思いを込めてである。eスポーツに関わるのはチームや選手、興行関係者だけではない。ゲームを開発し、運営する更に多くの人によって支えられている。eスポーツはゲームという土台の上にあるからこそ、豊かなコンテンツなのだ。
ゲームに新キャラクターを登場させよう。プログラマーはもちろん、イラストレーター、声優も必要だ。PVの制作、そのビデオを流すSNSの運営はどうしよう。そうそう、プロデューサーが登場する生放送もやらないと……。
キャラクターにはストーリーがある。新しいアップデートで「オーバーウォッチ」のキャラクターの1人が同性愛者であることが明らかになった。そのことが競技に何か変化をもたらすか? もたらすかもしれない。同性愛に対する社会的な受容の度合いはあらゆる国で平等ではない。プレイヤーがキャラクターをピックしないという結果になる、かもしれない。ゲームの思想的な背景が競技に影響を与える可能性は十分にある。
ゲームは商品であり、競技であり、文化である。その多様な側面があるからこそ、ゲームは最高のエンターテインメントだ。ゲーム産業がパッケージ売り切り型のビジネスモデルから、長期運営型のモデルへと変化する中で、eスポーツという副産物が生まれ、何千万人が熱狂する産業へと成長した。その変化は現在進行形で、まだ終わる気配はない。
筆者は「eスポーツメディア」ではなく、「ゲームメディア」であるべきだと思っている。eスポーツという新しいシーンを深く理解するには、ゲームが生み出す商業的、文化的、社会的影響を理解しなければならない。
プロを目指す若者が何年もかけてあるタイトルを練習し、研鑽を重ね、プロチームに加入した。リーグ大会でもそこそこに活躍できるようになり、世界大会への出場が決まったその直後、収益の不信によりタイトルの運営が終わった。若者の今までの努力は企業の合理的な判断によって水泡に帰す……。
誰しもこのようなことが起こってほしくないと思っている、いつまでもタイトルが続き、大会が開かれればよいと思っている。しかし、eスポーツは企業にとってビジネスに過ぎない。タイトルの収益があがらないのであれば、eスポーツシーンは(企業にとっては)負債となる。
繰り返しになるが、eスポーツシーンは商業主義と不可分であるからこそ面白い。アップデートが繰り返され、巨額の賞金が提供されるのは、eスポーツがゲームという広大な産業の一部だからである。
eスポーツはスポーツではない。eスポーツはeスポーツというまったく新しい競技の形だ。eスポーツメディアはその事実から目を背けてはならない。
【あわせて読みたい関連記事】
私があえてesportsをディスる理由

2018年1月の福岡大での講義において、「ここで、あえてesports をディスっておきます」と切り出した和田氏。この記事では、本人がその真意と現在のesportsへの改善余地を述べる。











