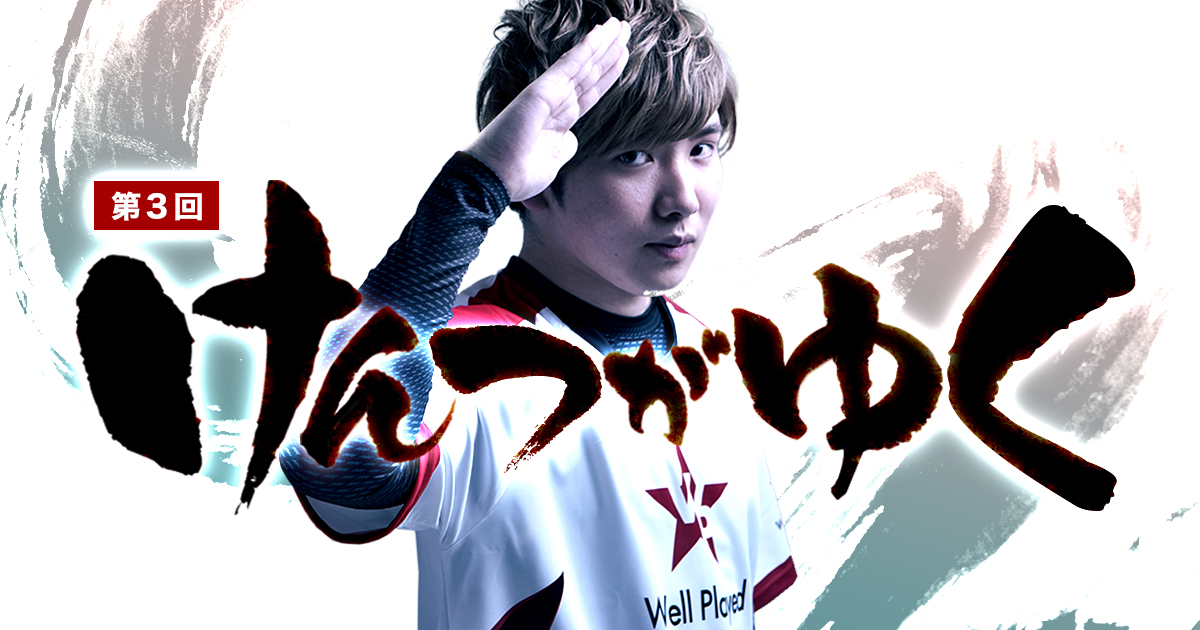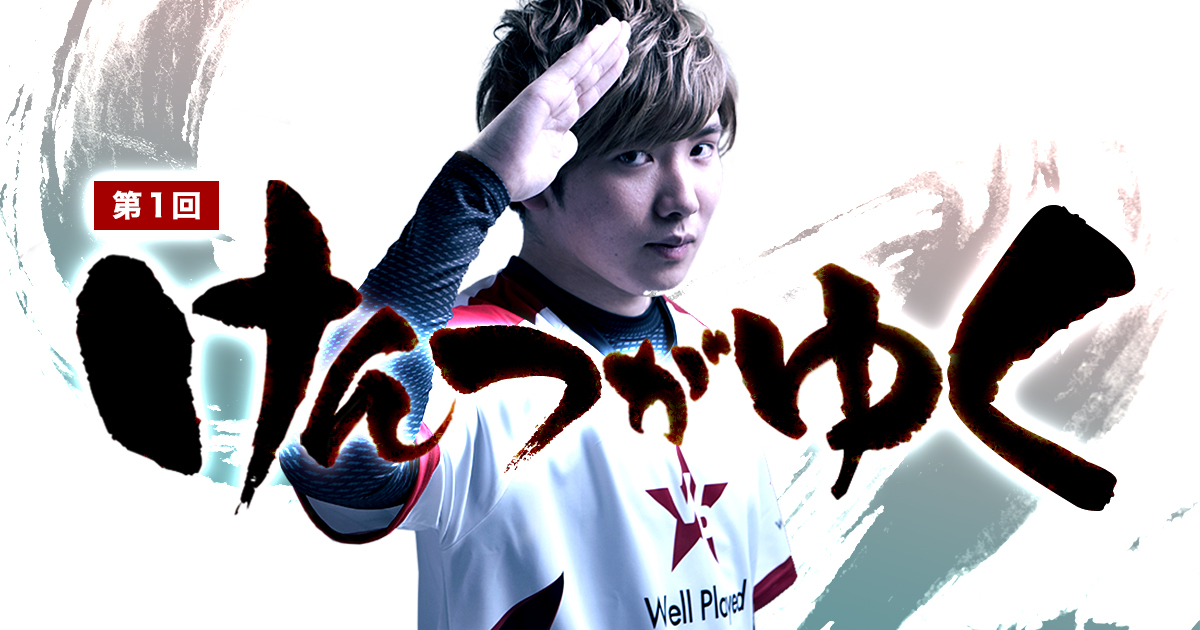【水谷隼×けんつめし対談】卓球もクラロワみたいですよね?(前編)

【この記事は約9分で読めます】
とある卓球練習場にて。
練習を終えて帰路につく選手たちとすれ違いながら、「クラッシュ・ロワイヤル」のプロゲーマー、けんつめし選手は待ち望んだ対談へと歩みを進める。
「水谷隼選手とサシ飲み。」
そう記された、今年2月に彼が投稿したTweetがことの始まりだ。
水谷隼選手とサシ飲み。
アスリートとして学ぶことが多かった…
リーグまでに絞ろう。
クラロワフレバト楽しかった😂
貴重なお時間ありがとうございました😊 pic.twitter.com/Jfadi34OTh— FAV|RB|けんつめし (@Kent_Golemeshi) February 6, 2019
全日本卓球選手権で史上最多の10回という優勝回数を誇り、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは日本人選手初のシングルスでメダリストとなった日本のエース、水谷隼選手。
この2ショットに不思議に思う人もいるかもしれないが、実は水谷選手はクラロワで最多トロフィー6,500超えまでやり込むゲーマーなのだ。
「卓球×クラロワ」
異なる世界のプロが向かい合ったとき、どんな会話のラリーがなされるか。
前編は2人の出会いから、卓球とクラロワに共通する“読み合い”へと話題が発展した。
クラロワのプロ選手に憧れる五輪メダリスト
――水谷選手がクラロワをプレイされていることはけんつめし選手とのTwitterでのやり取りを見て知ってはいたのですが、そもそもTwitterで絡みだしたのは何かきっかけがあったのでしょうか?
けんつめし:
確か、きおきおさんが先に水谷選手と絡んでいるのを見つけて、フォローさせていただいたのがきっかけでした。
卓球の選手でクラロワをプレイしている方がいるんだと思って。
水谷:
クラロワの前に「クラッシュ・オブ・クラン」(以下、クラクラ)を遊んでいたので、きおきおさんとかハルパパさんのクラクラ動画を見ていたんですよ。実はクラクラは卓球界でも流行っていて、25人くらいの選手がやってましたね。
その流れで、YouTubeでゲームの配信者がこんなにたくさんいるんだというのを徐々に知っていって、きおきおさんたちを知ったんです。
けんつめし:
確か迫撃砲を使っていることをTweetしていて。そこに自分が「迫撃砲、強いですよね」みたいな絡み方をして、返信いただいたのが最初だったような記憶があります(笑)。
それからはクラロワに関する投稿をされる度に絡ませていただいて、この前DMでお誘いしてついに食事をご一緒させていただいたっていう流れです。
お互いにTwitterはなんとなく見ていたって感じですよね?
水谷:
そうですね。
やっぱりTwitterでの交流がきっかけで、けんつのYouTubeはよく見ていましたし、クラロワリーグも毎回リアルタイムで見ていましたよ。
僕にとってクラロワのプロ選手は憧れなんです。

ほとんどの選手がYouTubeのチャンネルを持ってよく見ていますし、みんなそれぞれすごい上手いので憧れの目で見ちゃいますよね。けんつとはその中でも古くから交流があった選手になります。
けんつめし:
クラロワはSupercellさんがクラクラの次のゲームを出したということで、リリースされたタイミングでインストールしたんですか?
水谷:
そうですね。
水谷:
最初はそこまで熱が入らなかったんですけど、徐々にハマっていきました。
けんつめし:
最初はハマらなかった、というのは当時のクラクラプレイヤーたちの間でも言われていたみたいですね。それでも、途中から一気にのめり込んでいく人が多かったとか。
水谷:
あと、今はクラロワリーグができたことによって、視聴者としても注目したくなったというのはありますね。
トップの選手同士の試合が生で見れるのは、やり込んでいる自分としてはめちゃくちゃ楽しい。
けんつめし:
ドズルさんのチャンネルでやってる「クラロワコロシアム」にもコメントされてしましたよね。
フレンドなのでログインしているのをよく見かけましたし、試合数を見てもめっちゃやってるから本当にクラロワが好きで楽しんでいるんだなって思ってました。
水谷:
勝利数は1万回以上いってますから、結構やってますね(笑)。
真剣さと愛着が感動を生む
けんつめし:
クラロワリーグを見ていて、卓球界と相通ずるところがあったりしませんか?
水谷:
やっぱり関わってるみんながその競技が好きで、本気で向き合っているのは見ていて思いますね。
僕らは卓球ですけど、けんつたちはクラロワに本気で向き合っている。だからドラマが生まれて、感動が生まれる。
そこで生まれるノンフィクションのものは本当に素晴らしい。
クラロワリーグのドキュメンタリーとかも、すごくいい映像で感動しましたよ。
けんつめし:
僕の「アジア挑戦の記録 in 上海」っていう動画もあるんですけど、見たことありますか?
水谷:
あ、見たよ!
けんつめし:
あれがたぶんクラロワで初のドキュメンタリーで、自分のプロの業界に入り込む決心になったときなんです。あれは自分で見てもうるっときますね。
水谷:
やっぱりその人の思いを捉えた映像を見ると、すごく応援したくなる気持ちが生まれますね。
けんつめし:
逆に僕がクラロワと卓球について勝手に思ってるのが、基本は1対1の試合形式というところで似ていて、相通ずるところがあるのかなと。
水谷:
そうですね。あとは、ゲーム性がすごく深いじゃないですか。
相手のデッキを予測したり、出してくるユニットを先読みしたりと、深い読み合いがある。
自分がプレイしていればそういったところがわかるから、プロの試合も見ていて楽しいんです。
けんつめし:
ルールとかを理解した上でクラロワリーグを見るとわかりやすいので、試合を見ることが面白くてハマっていくというのはありますね。
水谷選手がクラロワリーグを見てくださっているのも、クラロワをずっとプレイされているからなのかなって思いました。

水谷:
あとはやっぱり選手たちへの愛着がありますね。それぞれのYouTubeをずっと見ていると応援したくなりますよ。
卓球もクラロワも戦術の読み合いが肝
けんつめし:
個人的に水谷選手に聞きたかったことがあるんですけど、聞いちゃっていいですか?
水谷:
全然いいですよ。
けんつめし:
先程もおっしゃっていましたけど、クラロワって読み合いがあるじゃないですか。卓球にも同じように読み合いがあるのかなって思うんですけど、クラロワみたいな読み合いがどういう場面であるのかがすごく気になります。
水谷:
確かに、卓球の試合は基本的に読み合いばかりと言ってもいいくらい。動体視力だけだと限界があるので、ほとんどは予測してプレイしています。
そこはやっぱクラロワと共通している部分と言えそうですね。
ただ、クラロワって1枚切ったらそのカードは次には出てこないじゃないですか?
卓球の場合は1枚切ったらまた次も同じカードがくることもあるというか、デッキの8枚が常に選べるというイメージです。
けんつめし:
そうなると読み合いとか予測が大事になってきそうですね……。相手の気持ちになって戦術を考えるとかはします?
水谷:
ありますね。
例えば、サービスって絶対に交互にやるじゃないですか? 相手がサービスのときは相手がどういうことを考えて自分の弱点を突いてくるのか、とにかく頭を働かせて考えます。
なので、卓球って試合が終わった後に疲れるのは、体じゃなくて頭って言われるんですよ。
常に頭の中で相手が何をしてくるのかを考えて、後はそれに対応できるスキル、相手の読みを外す、自分の技術の正確性、といったところで勝負している感じです。
弱点が1つでもあると、相手はそれを徹底的に狙ってくるので、その対応は常に考えないといけない。
けんつめし:
じゃあ、罠として弱点はあったほうが強いんですか?
水谷:
いや、絶対にないほうがいいです。弱点を攻められるし、そこを起点にいろいろなことをされてしまい、カバーできなくなってしまうから。
弱点がある時点でそこに意識を割いてしまうじゃないですか。意識できている分には弱点を突かれても大丈夫なんでしょうけど、ふとしたときに意識しなくなったとたんに攻め込まれてしまう。
なので、僕の考えとしては、基本的にはオールラウンダーというかなんでも器用にこなせる選手が生き残れます。
けんつめし:
クラロワもそうかもしれないです。
いろいろな戦術があって、それぞれに弱点もあるんですよ。
なので、弱点を取れるものに対して逆に対策をし返すみたいな読み合いが生じるんですけど、その中でミスのリスクが生じてしまうんです。
クラロワにおけるオールラウンダーって、いろいろなデッキや戦術を操れることだと思うんですけど、そうなると相手の戦術も自分が使ったことのある戦術になるので、「あ、俺だったらこうする」みたいことから逆算して考えられる。やっぱり弱点はないほうがいいなって思いましたね。

水谷:
卓球もクラロワも、そういう読み合いが好きなんですよね。
クラロワリーグだったらBANカードなどから相手のデッキを読むじゃないですか?
僕なんかはマルチやグランドチャレンジしかやらないからBANカードはないんですけど、例えば相手が2枚くらい出したらどんなデッキか予測できる。残りのカードが何なのかを読むっていうのが楽しい。
けんつめし:
卓球って中国が強いですけど、そういった読み合いが他の国より優れているんですか?
水谷:
そうですね。
読み合いを含め、選手がすばらしい能力、技術を持っていますが、何よりも指導者がすごい。卓球は1ゲームごとにタイムがあるのですが、そのタイムで戦術変換を上手くやっているんです。
けんつめし:
それってなぜなんですか? 知識が豊富にあるとか……?
水谷:
知識というよりは、研究に対する取り組み方ですかね。
大きな大会が終わった後って、中国では監督やコーチたちが2~3日もかけて集まり、研究をするためだけに時間を費やすんですよ。
その結果を選手たちに共有して試合に活かしているんです。
それができるのも、中国で監督になってる人たちが、オリンピックや世界大会のチャンピオンだから。オリンピックチャンピオンが監督で、なおかつ研究に膨大な時間を費やしているとなると、まずはそこが強さの秘訣かなという明白ですよね。

けんつめし:
日本の卓球界は、そこまでできていなんですか?
水谷:
そうですね、まだ研究が薄いですね。
それに、日本の場合は指導者不足というのもあります。卓球の指導者としてやっていける環境もまだ整ってない。
これは1人で練習してもどうしようもない差なので、中国から練習相手やコーチを呼んで、少しでも中国のものを取り入れようという努力をしています。
クラロワには指導者に関する課題みたいなのがあるんじゃない?
けんつめし:
どうですかね……。
今も各チームに監督がいますけど、技術は選手の方が圧倒的に高いんですよ。なので、監督の意見より選手側の意見がどうしても最終的に残るんですよね。
これはクラロワリーグの歴史が浅いのもあって難しい部分です。
水谷:
その気持ちはよくわかって、自分より実力がない人に何か言われたときに、やっぱり自分の意見を優先してしまう。
選手の方が圧倒的にスキルや経験が豊富なので、監督があまり意見ができないという構造はありますね。
(中編へ続く)
写真・大塚まり
【あわせて読みたい関連記事】
【水谷隼×けんつめし対談】クラロワがなくなったらどうする?(中編)
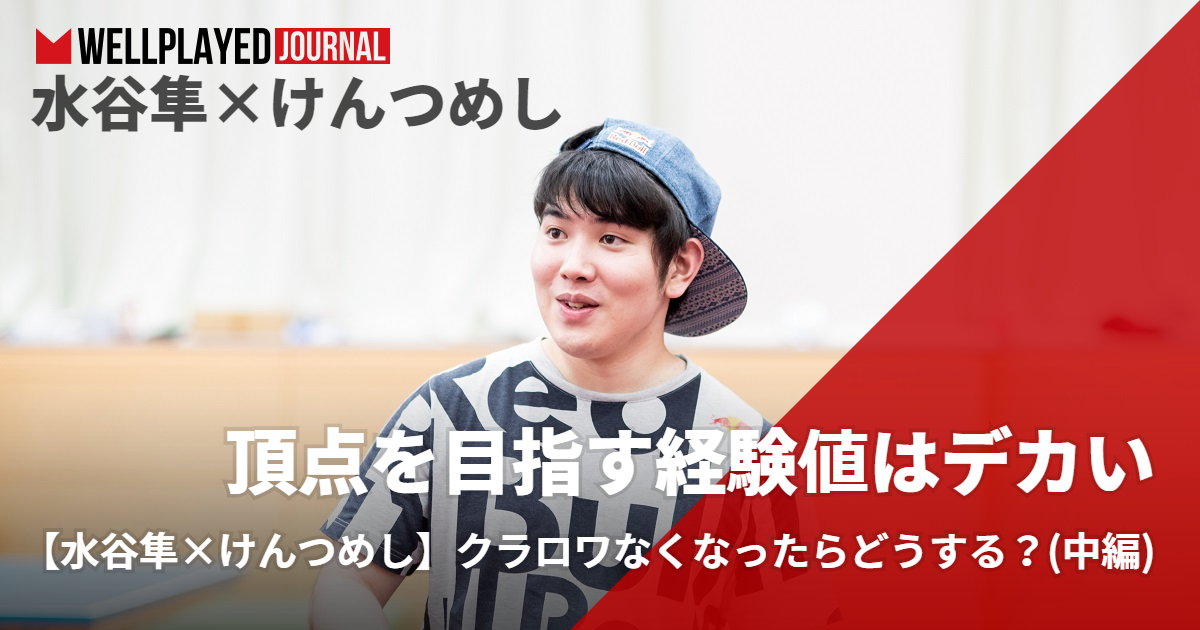
14歳でプロの世界に足を踏み入れた水谷隼選手。対するけんつめし選手はプロ2年目。「プロ」になることが意味するのは、もう後戻りできないということだという。